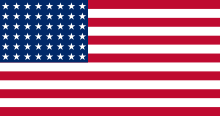助成先の活動紹介
産直ドミノ基金®の2022年度
助成先を訪ねてきました。
大森谷里山保全隊Rijin
大森谷里山保全隊Rijin
(兵庫県洲本市)
【 活動名称 】
地域の武器を作る
「竹原椎茸」 販売促進プロジェクト
大森谷里山保全隊Rijin
(兵庫県洲本市)
【 活動名称 】
地域の武器を作る
「竹原椎茸」 販売促進プロジェクト

▲ Rijin 谷口史朗さん、あわじ花山水 水野進さん、ドミノ・ピザ ジャパン 執行役員兼パートナーシップ部部長深澤勝
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 「竹原原木椎茸」を手にとるRijin 谷口史朗さん
谷口:龍谷大学の授業の一環でフィールドワークがあり、ここ洲本市「竹原」集落にも通ってきていました。
ここは、里山の風景が残っている素敵なところです。この集落の賑わいをもたらしている一つが、原木椎茸の観光農園でした。
原木栽培とは、天然の木を用いて、木を伐採して、枯れた丸太に直接種菌を植え付けてきのこを栽培する栽培法です。この丸太を「ほだ木」といいます。
このほだ木には、くぬぎ、ならを使っていますが、里山まで行って木を切ってきたり、ほだ木に菌が回った後に水につける作業は重労働で、高齢化のため、2018年に廃業されました。
大阪で会社員を3年務めて、退職。地域おこし協力隊として洲本市で働いた後に、そのまま移住することにしました。
「竹原」は、学生の頃からのネットワークがあることも、決め手になりました。
原木椎茸は、菌床しいたけに比べて、肉厚で風味が良いことが特徴です。
原木椎茸の観光農園を復活することで、島の内外から人が訪れる、そのことで、「竹原」の認知があがることを願っています。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされますか

▲ 竹原原木椎茸観光農園の椎茸
谷口:助成金では大きく3つのことを目指しています。原木椎茸のほだ木を寝かす施設の設置、商品化に役立てる機械の導入、そして商品化です。
ほだ木に菌を入れて、採取できるまでには2年かかります。現在の施設で2500本のほだ木を安置できますが、観光農園を運営していくには、足りる量ではありません。新たにつくることで、プラスで3000本を収容できます。
椎茸を形よく育てる過程で、椎茸を間引くのですが、それを美味しく乾燥させる若しくは商品化のための真空パックをする機械の導入をしたいと思っています。そして、その商品を販売するための商品開発とパッケージデザインを進めています。
使途の制約が少なく、チャレンジができる助成金なので、すごく応援してもらえていると感じます。
Q:10月8日に竹原原木椎茸観光農園を再開!

▲ 谷口さんと深澤さん
谷口:今年10月8日に「竹原原木椎茸観光農園」を再開させることができました。既に廃業されていた農家の水野さんからノウハウを伝授していただき、継業させてもらいました。
ここまでスムーズに再開させることができたのも、100種類以上もある椎茸の菌の中から、この土地の気温や湿度、環境に適した、椎茸が美味しく育つ最適な菌を、経験から、教えていただいていて、今もアドバイスをいただけるお陰です。
再開からこれまでに、60-70人のお客様に椎茸狩りにきてもらえることができました。近くの幼稚園の子どもたちにも来てもらったのですが、売っている椎茸が嫌いな子どもでも、ここの原木椎茸を食べたとお母さんたちから聞きました。育っているところを見てもらい、椎茸狩りをして親しんでもらえることは大切だと思います。そして、島外からも足を運んでもらえる方もいらして、この観光農園がなければ、ここまで来ることはない方たちです。美味しい椎茸を通じて、「竹原」の名前を知ってもらい、この素晴らしい里山の自然が作る「竹原」ブランドの「原木椎茸」を世に発信していきたいと思います。
Q:今後の予定を教えてください

▲ 切り方と味付けの異なる椎茸チップスと乾燥椎茸
谷口:11月初めには、準備していた椎茸はすべて採り終わる予定です。
耕作放棄地になっていた畑には、完全無農薬の原木椎茸のほだ木を安置するハウスを建設中で、地域の方の協力をもらって自分たちで作りました。今、7割程度できたところで、11月には完成をめざしています。紅葉が終わるころになれば、くぬぎを森に切りに行く予定です。この里山の風景を守るためにも必要なことです。
乾燥した椎茸チップは商品化に向けて、いろんな味付けを試しているところです。また、竹原原木椎茸のロゴはカッコよくデザインできました。乾燥機か真空パックの機械を導入し、商品化と販売できる商品力を高めていきます。
原木椎茸ができるまでには、ふた夏かかります。竹原原木椎茸観光農園がますます賑わい、ここ「竹原」のブランドを広めていかれるように、挑戦は続きます。

▲ 建設中のほだ木を安置する施設
大森谷里山探検隊Rijin事務局
谷口 史朗(たにぐち ふみお)さん

▲ Rijin 谷口史朗さん
竹原集落は、人口3世帯6人のいわゆる限界集落で、地域住民の高齢化に伴い農地の担い手不足などの様々な地域課題に直面していました。
いつか地域のために仕事をしたいと思っていた想いを、大学生だった頃に、フィードワークの授業で通ってきていた地域で、叶えることができて、移住してきて3年になりました。
竹原集落で地域の特産品の原木椎茸を復活させることができて、まずは一歩達成できたと感じます。大学生のころは、京都でよくドミノのピザを食べていました。この助成金の初回の支援をもらえて、嬉しいです。
今後は、「竹原原木椎茸」のブランドを発信すると同時に、特産品が販売できるレベルにできるように、パッケージのデザインなども進めていきます。
現在も、龍谷大学の学生を受け入れています。若い学生たちが定期的に地域に通ってきて、農業の担い手となり、関係人口が生み出される構造が築けています。
今後も、都市部と農村の交流の仕組みをつくり、「竹原」の素敵な里山が守られるように、地域の活性化のためにつなげていきたいと思います。
りゅうのひげ会
りゅうのひげ会
(新潟県新潟市)
【 活動名称 】
伝統野菜で黄菊の畑ひろがる
産地づくり目指すを
地域活性事業
りゅうのひげ会
(新潟県新潟市)
【 活動名称 】
伝統野菜で黄菊の畑ひろがる
産地づくり目指すを
地域活性事業

▲ りゅうのひげ会 小倉壮平さん、長津正男さん、生産者の皆さん、ドミノ・ピザ ジャパン CEO マーティン・スティーンクス、COO ベン・オーボーン
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 小倉さん(一番左)と長津さん(左から二人目)にレクチャーを受けながら、「りゅうのひげ」を収穫するマーティンとベン
小倉:2002年の冬に武蔵野美術大学の学生として、新潟市の岩室温泉のアートイベントに参加したのが、この地域との最初の出会いでした。その後、「新潟市岩室観光施設いわむろや」の館長のお話をいただき、12年前に移住してきました。
「りゅうのひげ」」のことは、その観光施設の館長をしていた時、地域の人から、毎年11月頃になると「昔、お殿様が好んだ美味しい菊があった」とたびたび聞くことあったのがきっかけです。
この地域に伝わる伝統食用菊を探したい、その菊をシンボルに温泉地観光を活性化させたい、そんな想いで探しました。
探し当てたのは、2013年の冬、ちょうど今日のような肌寒く雪交じりの雨が降るような日のことでした。近所の方の私有地に2株残っているのを見つけたのです。
それをお願いしていただき、自然栽培を専門とされる長津正男さんに託し、2年かけて復活させていただきました。2016年には、仲間を募集して4人でさらに株を増やす活動をスタート。2017年は他の食用菊の生産地の視察に行き、流通や加工を学びました。2019年にはグルメ&ダイニングスタイルショーに出展して、「りゅうのひげ」のPRに努めてきました。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされますか
小倉:「りゅうのひげ」を無事に復活させて、今では約10人の農家さんにご協力をいただきながら、600株にまで増やすことができています。次のステップを考えた時、この伝統食用菊を将来に向けて絶やさないためには、「りゅうのひげ」の流通と加工に本格的にチャレンジしたいと強く思っていました。助成金で目指しているのは、(1)すべての「りゅうのひげ」を売って収益にすること、(2)「りゅうのひげ」をレストランや生産者に知ってもらうこと、そして(3)「りゅうのひげ」生産にかかわるメンバーの後継を育てることです。
2017年に他の食用菊の生産地を視察して流通や加工について得た学びをこの助成金でいよいよ本格的にチャレンジしています。乾燥機の購入や販路拡大に向けた現地視察会等、やってみたいと思っていたことを実現に移していっています。

▲ 長津正男さんが栽培されている「りゅうのひげ」
産直ドミノ基金は、使途の制約が少なく、申請書類も煩雑ではないので、専従職員がいない私たちの活動にはとてもありがたかったです。「りゅうのひげ会」の取り組みは、小さな活動ですが、ドミノ・ピザのような大きな有名企業が支援してくださることで知名度も上がると思います。
Q:「りゅうのひげ」をどんな思いで栽培復活させてきましたか

▲ 「りゅうのひげ」を復活させた、りゅうのひげ会 生産部長の長津正男さん
長津:菊の栽培はずっとしてきたし、周りでもみんな作っています。しかし、この「りゅうのひげ」を見せてもらって、この香りと鮮やかな色に、こんな食用菊があったのかと衝撃を受けました。この地域の昭和一桁代の人には知られていますが、それ以降の世代は知らない伝統食用菊です。やっとの思いで小倉さんたちが見つけてくれた、大切な2株を預かったわけですが、実際に栽培してみると、とても繊細で戸惑いました。
しかし、昔からこの土地で愛された食用菊をなんとか復活させたいという想いで取り組んできました。こんな鮮やかな食材はほかに見当たらないので、貴重だと思います。この「りゅうのひげ」の栽培を、若い世代にも継いでほしいと願っています。
11月末から今年の「りゅうのひげ」を収穫!乾燥加工も改善!
小倉:「りゅうのひげ」は11月後半に最盛期を迎えます。収穫繁忙期は1週間で、フレッシュな食用菊が販売できるのはおよそ3週間ほどです。この伝統的食用菊を絶やさないためには、年間を通じた収益が得られる商品を作り、従事者を増やすことが必要です。
「りゅうのひげ」を加工した商品としては、寿司酢、佃煮、菊茶の3つを販売しています。寿司酢は、この地域のお殿様が昔、りゅうのひげをつかった菊ご飯を好まれたという言い伝えを聞いたので、最初に開発しました。

▲ 「りゅうのひげ」の寿司酢、佃煮、菊茶

▲ 乾燥した菊
グルメ&ダイニングスタイルショーに出展した時に、「菊を食べるのか。」と沢山の方に興味を示してもらいました。
「りゅうのひげ」は香り豊かで、色が鮮やかで、食感もとても良い食材です。また乾燥して菊茶としていただくことで目に効能があるとされているそうです。
産直ドミノ基金の助成金で、本格的な乾燥機を導入できたので、「乾燥菊」の商品化を進めていきたいと思っています。
視察を終えて

▲ 左から小倉さん、長津さん、マーティン、ベン
マーティン:地域の小さなプロジェクトを支えることはとても意義があります。地域は人が作るものです。ドミノ・ピザは、「ピザでつながる」をパーパスにしてビジネスを行っています。今日は、ここ新潟市西蒲区の岩室温泉で、「菊でつながる」コミュニティづくりに触れることができ、とても感銘を受けました。
ベン:2株しか残っていなかった食用菊を復活させよう。地域の活性化に活かそうというその高い目的意識に感動しました。チャレンジは人々から支持され、そしてハードワークは実るものです。
Q:今後の予定を教えてください
小倉:今回の新しい本格的な乾燥機を導入するまでは、家庭用の乾燥機を使っていたので、生産量に追い付かず、「りゅうのひげ」をすべて商品化することができず、フードロスも生んでしまっていました。この乾燥機でその問題も解決できます。
香りの特徴を活かして、京都のシェフから「りゅうのひげ」のシロップをつくってみようかというお引き合いをいただいています。収穫期が終われば都内のマルシェに出向いて商品の販売も行っていきます。
地域農産物の販売を促進し、「りゅうのひげ」生産にかかわる人の継続的なかかわりを可能にし、この地域が活性化できることを目指して、今後も活動を続けてまいります。

▲ 「りゅうのひげ」の乾燥機にかける小倉さんと長津さん
りゅうのひげ会 事務局
小倉 壮平(おぐら そおへい)さん

▲ マーティンとベンと一緒に「りゅうのひげ」を収穫する、りゅうのひげ会 小倉壮平さん
岩室温泉は弥彦・多宝山の山裾にあるなんだかホッとする小さな温泉地です。ここ新潟には四季があり農作物がとても美味しく、東京出身の私は豊かな食文化に魅了されていました。
そして、学生の頃からお世話になってきたこの地域の人たちとの思い出を振り返り、自分を頼りにしてもらえるなら恩返しをしようという気持ちもあり、移住してきました。
実は今、「りゅうのひげ」を育ててもらっているのは、月2回、農家レストランを開催した時にお世話になった農家のお母さん達です。地域のつながりを作りながら、活動ができています。
「りゅうのひげ」の花部分を採取することを「もぎる」と言います。「りゅうのひげ」の収穫は小さな子どもにも簡単にできるので、来年は子どもにも参加してもらって、「もぎるスピードコンテスト」を開催してみようかと思案しています。
次の世代を担う子どもに、「りゅうのひげ」に親しんでもらうことも伝統野菜を守るために必要なことだと思います。
また、お取引先を増やすことで、生産にかかわる人も増やし、作付面積を増やすこと。そして、この西蒲区の岩室温泉に、黄色一面の「りゅうのひげ」が咲き誇り、一面黄色の菊畑の写真を撮影して全国に発信していきたいです。
子ども食堂虹の花
子ども食堂虹の花
(高知県土佐清水市)
【 活動名称 】
米粉で感動を!
日本の食文化を見直す子ども食堂
子ども食堂虹の花
(高知県土佐清水市)
【 活動名称 】
米粉で感動を!
日本の食文化を見直す
子ども食堂

▲ 左から 子ども食堂虹の花 副代表 松岡素美子さん、代表 松岡修一朗さん、ドミノ・ピザ ジャパン COOベン・オーボーン、子ども食堂虹の花 事務局次長 松岡誠一さん、子ども食堂虹の花 事務局長 中山義介さん、ドミノ・ピザ 増本鉄平オーナー
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 子ども食堂の開催にあたりドミノ・ピザ ベン・オーボーンに取り組みを紹介する松岡修一朗さん
松岡:私たち「虹の花」は、土佐清水市で県社会福祉協議会、市社会福祉協議会、清水高校・中村高校などの高校生ボランティアらと連携して「子ども食堂虹の花」を運営しています。毎月1回約200人以上の参加者を得て、多世代コミュニティの創出、地域活性化に取り組んでいます。
子ども食堂を実施するなか、「日本の食文化であるお米を多くの子どもたちに食べてもらいたい」、「高齢化で担い手のない農業の素晴らしさを子どもたちに伝えたい」と考えるようになりました。それにはまずお米の素晴らしさを伝えることが一歩です。そこで、子どもたちに、グルテンフリーということで近年再評価されている米粉に感動を見出してもらい、日本の食文化を見直してもらう活動を実施することとしました。
地元の田んぼで収穫したお米を乾燥・脱穀・精米した後、ドミノ・ピザが出捐する「産直ドミノ基金」の助成金を活用して導入した米粉製粉機と米粉製麺機で、米粉やうどんを製造。うどん料理やお菓子をつくって子ども食堂にて提供することで米粉の可能性や農業の素晴らしさを子どもたちに伝える活動を始めました。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされましたか
松岡:この助成金のお陰で、念願だったお米を米粉に粉砕することのできる「粉砕機」を買うことができました。この粉砕機でつくった米粉を使用して、グルテンフリーで安心な「米粉たい焼き」や「米粉クッキー」さらには「米粉うどん」など、米粉を使用したお菓子や麺をつくり、子ども食堂で提供しています。

▲ 米粉で作るグルテンフリーの「米粉たい焼き」を焼く松岡誠一さん

▲ 米粉で作るグルテンフリーの「米粉たい焼き」を焼く松岡誠一さん、お米を米粉に粉砕できる「粉砕機」と粉砕された米粉
毎月1回開催している子ども食堂では、子どもや親御さんに、米粉を使用したグルテンフリーの食べ物を召し上がっていただく事で、米粉の素晴らしさや米粉の活用方法などを伝えることができています。
また、子ども食堂の活動では、持続可能な取り組みを行うことも大切だと感じています。この度の助成金で購入できた「粉砕機」を活用して、持続可能かつ安全で栄養のある米粉を多くの方に提供できる事を、とても嬉しく思います。
2023年5月21日に「米粉体験学習会」を開催!

▲ 「米粉体験学習会」開催の様子
松岡:2023年5月21日に「米粉体験学習会」を開催し、米粉の粉砕体験や米粉の活用方法、汎用性を学習いただきました。
学習会では地元の子どもを中心に、高校生や大人約20名の方にご参加いただく事ができました。「産直ドミノ基金」の助成金を活用して導入した米粉製粉機を使用し、実際の粉砕作業と同様の過程を体験していただきました。
さらに学習会では、「なぜお米を米粉にするのか」、「お米と米粉の違いについて」、「米粉がもつ可能性」について、学習していただきました。耳で聞いて学んで、目で見て体験して、実際に米粉ができるまでの過程を楽しんでいただく事で、米粉に興味や親しみをもってもらうことができ、地元の皆様にとって学びのある、良い機会に繋がったと感じています。
米粉を通して、「お米」の魅力をしっかりと伝え、もっと身近な食材として活用していただけるように、引き続き「米粉体験学習会」を行っていきたいと思います。
Q:今後の予定を教えてください
松岡:今度は米粉を使用したレシピの開発や、「米粉たい焼き」のチョコ味など、米粉を活用したお菓子や食事のレパートリーを増やしていきたいと考えています。「米粉たい焼き」に関しては、まだまだ改良の余地があるのでさらに美味しくなるように試行錯誤し、最終的に新しい味の展開ができればと考えています。これからも汎用性の高い米粉を活用して、誰もが安全に、おいしく食べれる子ども食堂虹の花オリジナルのメニューを開発にチャレンジしていきます。
さらに清水高校・中村高校のボランティアの皆さんに協力いただいて、多世代コミュニティを創出し、土佐清水市をはじめとする、地域活性化を目指していきたいと考えております。

▲ 「子ども食堂虹の花」に参加する高校生ボランティアの皆さんと松岡さん
子ども食堂虹の花
代表 松岡修一朗(まつおかしゅういちろう)さん

▲ 子ども食堂虹の花 松岡修一郎さん(写真右)
土佐清水市は、高速道路や鉄道が通っていないこともあり、東京から移動時間を最も要する都市のひとつと言われている、綺麗な川や自然のぬくもりがあふれる土地です。現在では少子高齢化における農業担い手の減少や耕作放棄地の増加が進んでる背景があり、愛する地元を守りたい、という気持ちから、農業のすばらしさを子どもたちに伝える活動、子どもたちの食生活改善、お米の消費量増加、グルテンフリーの米粉を普及させる活動行うことにしました。
家族の助けも借りて開催した当初の子ども食堂では、20名~30名の参加でしたが現在では毎月200名の方に、「米粉学習体験会」開催日は240名以上の方にお越しいただくことができています。
地元の高校生や地域の方と一緒にお米に関わることで、農業の担い手減少や耕作放棄地増加などの地域課題への関心を高め、農業の素晴らしさを伝えるとともに、米粉を活用することで、子どもたちの食生活改善、お米の消費意識向上に成功していると感じます。
今後も米粉を通して、農業を守る持続可能な仕組みをつくり、地域の活性化につなげていきたいと思います。
特定非営利活動法人ぱるぱる
特定非営利活動法人ぱるぱる
(奈良県奈良市)
【 活動名称 】
不揃いの廃棄椎茸を
椎茸パウダー(申請時は、粉末だしの素)に変身加工
特定非営利活動法人ぱるぱる
(奈良県奈良市)
【 活動名称 】
不揃いの廃棄椎茸を
椎茸パウダー(申請時は、粉末だしの素)に
変身加工

▲ 右から 梁本美乃理(ドミノ・ピザ 営業部スーパーバイザー)、石丸浩子さん(ぱるぱる 理事長)、西馨さん(ぱるぱる 利用者)、松原歩(一般社団法人産直ドミノ基金 代表理事)、有馬敏幸(ドミノ・ピザ 営業部スーパーバイザー)
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 特定非営利活動法人ぱるぱる 理事長 石丸浩子さん
石丸:特定非営利活動法人ぱるぱるは、2017年6月から活動を始め、2018年1月に法人化しました。奈良市の障害福祉サービスの指定を受けて、相談支援事業所あいあい、居宅介護事業所てくてく、生活介護事業所おるおる、福祉施設事業所みりみり、グループホーム福を設置して、地域で生活する高齢者や障がい者に、自分らしく自分の人生を生きるための支援を行い、全ての人々が健やかに暮らせる地域社会づくりを進めています。
福祉施設事業所みりみりは、視覚障がいを主として支援をしており、スーパーの袋詰め作業や農作物栽培と販売も行ってきています。しかし、農地への移動が困難な視覚障がい者もいるため、そんな利用者の方たちに携わっていただけるお仕事を探してきました。
そんななか、室内で椎茸を栽培されている方と出会いました。そして、2021年3月から視覚障がい者の方と共に、室内菌床椎茸の栽培に従事し、販売してきました。 しかし、傷が付いたり、不揃いの為、店頭販売できずに廃棄される椎茸がありました。有効活用できないものかと、廃棄される椎茸を乾燥し、コーヒーミルで粉末にして試しに直売所で販売してみたのがきっかけです。視覚障がい者の方の、優れた手の触感で、販売対象外の椎茸を選び出し、廃棄対象の椎茸を無駄なく椎茸パウダーに加工作業を行っています。
椎茸パウダーは、椎茸嫌いのお子様にも食べやすく、椎茸パウダーを使った煮物、吸い物、炒め物などの椎茸風味の出汁の美味しさは、好評をいただいています。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされますか
石丸:椎茸の栽培、収穫、椎茸パウダーへの加工を行うために、どのように粉末にするとより良いのか、試行錯誤を行ってきました。視覚障がい者の方でも簡単に作業を行うことが出来て、より素早く溶け、より滑らかなソフトな粉末にするために悩んでいたところ、今回ドミノ基金を知り、助成に応募させていただきました。
今回の助成金にて食品粉砕機と椎茸完熟菌床を購入し、規模を拡大して椎茸パウダー製造の取り組みを進めることが出来ています。
椎茸をまるごと粉末にした栄養たっぷりの美味しいだしを皆様の美味しい料理の中に加えていただきたいと思っています。

▲ 乾燥した椎茸を粉末にする様子
Q:どんな思いで椎茸栽培と加工を行ってきましたか

▲ 収穫時期の椎茸を確認する西馨さん
西:82歳の時からぱるぱるを利用し、今年で8年目になります。自身の健康のために指先を動かして出来る仕事をしたいと思っていたところ、石丸さんから「椎茸を使って事業をしたい」とお話しを聞き、すぐに賛成をしました。ここでは、視覚障がいのある皆で、椎茸の栽培や加工作業だけでなく、その他にも畑で様々な野菜作りに励んでいます。
視覚障がいのある私たちにこうしたお仕事や居場所があること、今回ドミノ・ピザ様に助成をいただきましたこと、大変感謝しています。
Q:5月25日おにぎり屋さん「ぱくぱく」をオープン!
石丸:視覚障がい者らが中心となって栽培している椎茸や、椎茸を乾燥させて粉末に加工しただしの素、畑で収穫された野菜を事務所ビル前で、直売していました。無農薬の新鮮な美味しい野菜や椎茸をそのまま味わっていただきたい、という思いからおにぎり屋さん「ぱくぱく」をオープンさせることとなりました。

▲ 2023年5月23日にオープンしたおにぎり屋さん「ぱくぱく」。お店の営業時間は平日午前11時~午後2時半。お問い合わせは、特定非営利活動法人ぱるぱる(電話:0742―93―4186)へ。

▲ 椎茸パウダーで炊いたおにぎり2個、お味噌汁、小鉢にコーヒーか紅茶が付いて税込み500円。うち100円は盲導犬育成の寄付金になる。
視覚障がい者の方が中心となって、おにぎりと椎茸の椎茸パウダーを使ったお味噌汁、畑で採れた野菜を使った小鉢を作り、椎茸の椎茸パウダーで炊いたおにぎりをセットにして販売しています。
5月3日にプレオープンを行い、この度5月25日にオープンをさせていただきました。是非、多くの皆様に美味しいおにぎりや野菜を味わっていただきたいと思います。
Q:今後の予定を教えてください
石丸:今回、ドミノ・ピザ様に助成をいただき、椎茸の栽培や加工もよりスムーズに行うことが出来るようになりました。今後はもっと椎茸栽培や販売の範囲を広げながら、より多くの皆様に味わっていただけるように活動をしていきたいと思っています。
椎茸パウダーは、乾燥椎茸販売よりも粉末にする手間がかかります。障がい福祉の活動を通じて、製造・販売を行うことでご家庭の食卓に美味しさと健康をお届けしたいと願っております。

▲ 不揃いの廃棄椎茸が椎茸パウダーに変身。スパイスボトル入り椎茸パウダーは400円(内容量20g)。詰め替え用椎茸パウダーは、400円(内容量40g)。 スパイスボトル入り椎茸パウダーと詰め替え用椎茸パウダーのセットは、750円。化粧箱は別途200円。
特定非営利活動法人ぱるぱる 理事長 石丸浩子さん

▲ 「おにぎり屋 ぱくぱく」の開店をお祝いする視覚障がい者、特定非営利活動法人ぱるぱるのスタッフとドミノ・ピザ関係者
産直ドミノ基金の助成金のことは、実は、おひとりの理事が見つけて応募しました。助成が決まり、活動を広げることが出来ています。
「美味しかった」という声いただけるのが、何より励みになります。ぜひお近くにお越しの際には、椎茸が香るおにぎりを「おにぎり屋 ぱくぱく」で味わってください。
活動に関わる方たちの想いをつなぎ、地域の福祉を増進させる活動を続けてまいります。
両向自治公民館
両向自治公民館
(岩手県気仙郡住田町)
【 活動名称 】
岩手県住田町・特産品料理教室
インストラクター育成講座
両向自治公民館
(岩手県気仙郡住田町)
【 活動名称 】
岩手県住田町・
特産品料理教室
インストラクター育成講座

▲ 岩手県住田町・特産品料理教室 インストラクター育成講座 受講者の皆さんと、両向自治公民館(主事)堀尾昌史さん(3列目)、「ワイン食堂 ケラッセ東京」坂東誠シェフ(1列目左から2人目)、両向自治公民館青年部・地元生産者 での園 水野孝洋さん(2列目左はし)
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 坂東シェフと談笑しながら、調理を行う受講生のみなさん
堀尾:岩手県住田町の畜産、稲作農家が中心になり、何か地域の活性化ができないかと考え、東日本大震災発生時の被災者支援にご尽力いただいた東京のシェフとのつながりを活かして、地域を活性化するチャレンジを行うことにしました。
活動を始めた当初は、両向自治公民館青年部のメンバーと単発的な料理教室やオンラインの料理教室を行ってきました。何度か回数を重ねて実施するごとに、一人のシェフでは料理教室の開催に限界があるため、シェフ仲間を増やしていきたいと思い、インストラクターの養成講座を考え付きました。
料理教室の講師を増やしていくことにより、住田町の美味しい食材を活かした料理を町外や県外をはじめ、様々な場所で提供でき、多くの方々に地元食材の魅力に気づいてもらうことで、住田町の地域活性化につながるものと考えています。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされますか
堀尾:このたびの助成金で、岩手県住田町の畜産物・農産物を使った料理教室のインストラクター養成講座を隔月で計6回開催することができました。講座終了後、最終試験を行い、作った料理を生産者の農家さんが試食します。合格者には、認定証を授与し、インストラクターとして料理教室を開くことができるようになります。*
インストラクター養成講座の講師には、東京・新宿のシェフ 坂東さんにお越しいただき、12名の受講生が参加しました。講座で使用する食材は、地元生産者から提供してもらいました。

▲ 坂東シェフが受講生のみなさんにレシピをレクチャーしている様子

▲ インストラクター養成講座 座学の様子
生産者にとっては、インストラクター養成講座を通して、受講生と直接交流を深められ、丹精込めて育てた食材がどう料理されて、どのような評価をされているのかを感じる事ができる機会となりました。生産意識の向上にもつながっているといいます。 食材に関わる人が増えることで、生産の基盤である地域の大切さの発信力・拡散力を高め、町内の内側からも地元の食に対する意識を高めて“美味しい食材が揃う住田町”を活性化する事ができていると感じています。
* 2023年7月30日に最終試験を行い、8人の受講生がインストラクターに合格されました。
インストラクター養成講座では料理を作ることはもちろん、シェフと同じように食材や料理の魅力を発信していただきたいという思いから、住田町や美味しい食材の知識を学んでいただく座学の時間も設けました。ミネラルが多い水の勉強や、使用する食材の美味しさの特徴などを生産者に語っていただくことで、生産現場の生の声を、受講生の皆さんに届けました。
Q:どんな思いで岩手県住田町・特産品料理教室 インストラクター育成講座の講師をされてきましたか
坂東:岩手県住田町は、地元の皆さんが思う以上に、魅力的な食材に溢れています。日本トップレベルの住田町の食材の魅力が全国へ届いて欲しい、という熱い思いでインストラクター講座の講師を担当させていただきました。
インストラクター養成講座では、「なんでもスパニッシュオムレツ」など、特定の食材が揃わない場合でも美味しい料理が作れるようになるよう「なんでも」がついたレシピを用意しました。今後、料理教室の講師として活躍していただく事を考えた、養成講座ならではのレシピです。
実際の講座では受講生の皆さんが、度肝を抜かれるくらいやる気に満ちており、とても驚きました。インストラクター養成講座が始まる前は難しくて挫折する方もいるのではないか、と内心思っていました。

▲ 「ワイン食堂 ケラッセ東京」 坂東誠シェフ

▲ 「なんでもスパニッシュオムレツ」のレシピと、住田町の特産品食材
しかし、初回から6回まで、すべての講座を通して、受講生の皆さん全員が意識を高く持ってチャレンジしていらっしゃいました。途中で抜ける方もいらっしゃらず、継続して、楽しく学んでいただき、住田町の美味しい食材を、本気で広めたい!と思っている気持ちがよく伝わってきました。
受講生の皆さんがそれぞれのお立場で料理教室を開催する事により、住田町の美味しい食材を使用した料理や食材の魅力が日本全国へ届くと信じております。そして、その日を楽しみにしております。
Q:今後の予定を教えてください
堀尾:このたびの助成金で、インストラクター養成講座第一期を開催し、大きな手ごたえを感じられたことから、第二期の開催の検討を進めております。そのためには、助成金の手を借りずに、自立した活動にしていく事が大切だと考えておりますので、第一期生で講師となった皆さんと連携して、第二期の開催を進めていければと考えています。
また近年のコロナ禍や情勢不安がある中で、地元で作られたものを食べれる事に、改めて安心さを感じました。私たちの身近にある“食”について考えるだけでも、サステナブルにつながると感じています。

▲ 実際の料理教室で受講生が作成した「なんでもスパニッシュオムレツ」
今後も地域の皆さんや講師の皆さんと一緒に、住田町の食の魅力発信や食に携わる活動を続けて、生産者様の応援をするとともに、住田町の活性化に努めて参ります。
両向自治公民館事務局 堀尾昌史(ほりおまさふみ)さん

▲ 両向自治公民館 事務局 堀尾昌史さん(写真左)
住田町は人口5000人弱、総面積の89%が森林の自然に囲まれた、畜産や稲作農業に関わって暮らす方が多い街です。近年は、少子高齢化が進み、超高齢化社会の問題も抱えています。そこで、農業の担い手を増やしていくために、食材の魅力を伝えるイベントを行って参りました。
今回、インストラクター講座の講師を担当していただいた坂東シェフとは、東日本大震災発生時の被災者支援で出会いました。坂東シェフは、震災後しばらくの間、被災者のために住田町のレストランにて、料理を振舞っていらっしゃいました。
「坂東シェフの料理を食べたい」と、車で1時間もかけてきてくれる方も多くいたことが、強く記憶に残っております。その当時より坂東シェフには住田町の食材をお褒めいただき、住田町の生産者も、「自分たちが育てている食材に、そんなにも魅力があったのか」と嬉しく話していました。
インストラクター養成講座を通して、畜産・農業従事者の方が、町外の消費者とのつながることで、生産者の生産意識を向上につながることはもちろん、販路の拡大による売上向上につながったと感じています。最近では、町内での地元食材の認知があがったためか、産地直売所のケースに並ぶとすぐに売り切れになってしまうようになりました。地元食材が知られ、地元で愛されていると実感します。
今後も、畜産・農業従事者の担い手を増やすために、農業魅力を様々な角度から伝え、さらなる住田町の活性化につながる活動を行っていきたいと思います。
山梨市ふるさと振興機構
山梨市ふるさと振興機構
(山梨県山梨市)
【 活動名称 】
地域文化を支える精神をもった
就農者を育成支援する
「山梨パラレル農家」制度の実証実験
山梨市ふるさと振興機構
(山梨県山梨市)
【 活動名称 】
地域文化を支える精神をもった
就農者を育成支援する
「山梨パラレル農家」制度の実証実験

▲ 一列目左から ドミノ・ピザ ジャパン CMO ムリナル・シンハ、山梨市ふるさと振興機構 代表 田中友悟さん、一般社団法人産直ドミノ基金 代表理事 松原歩、二列目左から日森康浩さん、日森清美さん
Q:この活動を始められた経緯を教えてください

▲ 左から日森農園でシャインマスカット狩りを行う、ドミノ・ピザ ムリナル・シンハと田中友悟さん
田中:前職だったまちづくり会社の業務で、山梨市の一次産業が抱える課題の調査分析に取り組みました。その活動を行うなかで、7年前に山梨市牧丘町を訪れる機会を得ました。山梨市の農業に関する知識がなかった私に、日森(ひもり)農園さんをはじめとする沢山の方が、地元の緑豊かな自然文化や、地域で受け継がれてきた歴史風土について教えてくださいました。そのお話に、深い感銘を受けた事を鮮明に覚えています。
このことがきっかけで、私のような山梨市にゆかりがないよそ者を快く迎え入れてくださる地域の皆さまの温かさを受け継ぎ、今度は私が、地域外の方を受け入れる立場になって貢献したいと思い、山梨市への移住を決めました。果物に代表される一次産業を未来へと受け継ぎ、新たなまちの担い手を、行政や、一次生産者である農家さんと橋渡しをする役割を担うため、「山梨市ふるさと振興機構」を設立しました。
設立以来、活動の幅を広げ、これまでに農作物の販売支援のほか、地域の人と新規就農者が一緒にまちの課題を考えるワークショップの開催、情報発信、デザインのサポートなど行ってきました。こうした経験を踏まえ、今回、新たに農業に関わりたい人たちの山梨市での体験を後押しし、農業に関わる機会や指導者の皆さんを紹介するための窓口の設置を行いたいと考え、産直ドミノ基金®へ助成金の応募させていただきました。
Q:産直ドミノ基金の助成金でどんなことをされますか
田中:助成金では、地域文化を支える精神をもった就農者を育成支援する「山梨パラレル農家」制度の実証実験を行いました。「山梨パラレル農家」制度とは、就農希望者が自身のライフスタイルを考えながら、それぞれのペースで山梨市の第一産業に携わる方との関わりを築く事で、地元の文化を守り、支える精神を併せ持った新規就農者や移住者を育てる仕組みです。
「山梨パラレル農家」制度の有効性を実証するために、大きく分けて3つのチャレンジを行いました。

▲ 日森農園の様子

▲ 日森農園で育った、大きな実と甘みが特徴のシャインマスカット
1つ目は、農業を学ぶイベントの開催です。果樹農業の年間作業を知る実地体験などを行う事で、山梨市の果樹農業の本質を伝え、就農の一歩手前となる入り口をつくる事ができました。
2つ目は、自然文化体験イベントの開催です。山梨市の土地の魅力や地元のライフスタイルを、遊びを通して伝えた事で、山梨市の地域文化に関する理解を深めていただくことにつながりました。
3つ目は、山梨市の民俗文化である「無尽(むじん)」を現代的に再解釈した「無尽交流会」の開催です。交流会では、農家や大学生など、様々な方が集まってまちの未来について意見を交わす場が生まれた事で、移住や就農希望者からの相談を受け入れられる体制を整えることができました。
この3つのチャレンジを1年間かけて継続的に行った結果、就農に関心のある方が、自分のペースで、山梨市の果樹産業について少しずつ理解を深めていく新しい機会と窓口をつくる事ができました。 産直ドミノ基金®のように、実験的な事業の立ち上げを支えていただける助成金は稀なので、非常に貴重でありがたかったと感じています。
Q:「山梨パラレル農家」制度の実証実験について
日森清美さん:日森農園は、昔からりんごを中心に栽培してきました。30年程前に、地域を支える付加価値の高い商品を作るため、ぶどうの栽培を始め、20年前に山梨市牧丘町で初めてシャインマスカットの原木を植えて大切に育ててきました。山梨市のシャインマスカットは日森農園から枝分けして広がっていったものです。
ぶどうを育てるためには、たいへんな労力がかかります。毎年、4月から不要な枝を切り始めます。4月から5月のぶどうの実が実り始める最も大切なわずか約2週間の間に、すべてのぶどうに、袋かけを行わなければなりません。

▲ 左から日森農園を運営する日森康浩さんと日森清美さん。中央には山梨市牧丘町で最初に植えたシャインマスカットの原木
この時期が一年で最も忙しくなります。短期間で膨大な作業をやり終えないといけないので、農園の運営をご引退された地域の皆さまがお手伝いにきてくれる事もあります。そうした沢山の皆さまの助けを受けながら、8月頃にかけて、おいしいぶどうの実が育っていくのです。我々農家としては大切な作業が集中する時期があり、その時に、多くの方々のサポートがいただければ、とても助けられます。
多くの農園では人手が不足しています。「山梨パラレル農家」制度を通じて、多くの方に、山梨市の地域文化や果樹産業を理解していただき、力もお借りして、美味しい果物の提供を続けていかれたら嬉しいです。
Q:今後の予定を教えてください

▲ 日森農園のシャインマスカットを収穫する田中友悟さん
田中:山梨市での新規就農や移住を希望する人に、最初に相談してもらえる存在を目指したいと考えています。そのために、果樹産業だけではなく、山梨市の文化や歴史など、このまちの全てを体験してもらえるサービスや交流会を展開していきたいと考えています。具体的には、今回の助成金を活用して生まれたネットワークを活かして、「完全就農」だけではない、果樹産業への多様な関わり方をつくりだしていきます。1日~2日などの単発的な体験だけではなく、中期的に山梨市へ宿泊する事ができる仕組みづくりを行っていくことで、移住者を増やすことにもつなげていきたいと考えています。今後も、山梨市の果樹産業の継承に貢献し、地域文化を体現する幅広い活動を行っていきます。
山梨市ふるさと振興機構 代表 田中 友悟 (たなかゆうご)さん
田中:山梨県山梨市は、東京など大都市との交通の便も良い事から、果樹栽培を中心とした農業や観光農業が盛んな地域です。「山梨市ふるさと振興機構」の英語名は、「Yamanashi Pride(フライド)」としています。山梨市のふるさとの風景と文化を守り、「山梨の誇り(プライド)を育てる」という想いがあります。なだらかな斜面や平坦地に果樹園が広がり、シャインマスカットをはじめとするぶどうの生産が盛んで、農園で四季を感じることができる、緑豊かなとても誇りを持てる場所です。山梨市の果樹園や農園で、様々な食べ物を育てるだけではなく、“その土地の風景をつくる”という思いで、まちづくりを行っていきたいと思います。

▲ 山梨市ふるさと振興機構 田中友悟さん